日本人は“森の民”である。
環境考古学者の安田喜憲氏はそういった。国土面積の7割が森、先進国の中でもフィンランドに次いで2位という世界でも有数の森林大国日本に根をはる私たちにとって、森は信仰・資源・レジャーなど、暮らしにおいて馴染み深い存在なのである。
では、その森で行う「森のリトリート」というものをご存知だろうか。
リトリート(retreat)という言葉は近年よく聞くようになったため、知っている方も少なくないだろう。英語でre(再び)treat(調える) と書き、仕事や家庭など日々の生活から離れ、自分だけの時間を持ったりリラックスしたりすることを通じて心をリセットすることである。ヨガや瞑想といったリトリートが注目されるなか、株式会社森へではこれを森で実践している。
リトリートと聞くと単なる“保養”とも聞こえるが、一体どのようなプログラムなのか。そして、なぜ森なのか。
その答えを探るべく、昨年12月冬至の日に開催された『Ecological Memes Forum 2019 〜あいだの回復〜』(動画はこちらから)にて行われた体験型セッションに参加してきたので、そこで感じた「森リト」のエッセンスを本記事にて紹介しよう。

「考えるモード」から「感じるモード」へ
体験セッションを先導したのは菊野陽子さんと鈴木宏和さん。株式会社森へのメンバーとしてこれまで多くの人を案内してきた森のナビゲーターだ。
本来、森のリトリートは
“森の中で深く内省し、互いに対話することで、自分自身や事業の原点について本質的な気づきや洞察を得るための2泊3日の合宿型プログラム”
となっていて、そこでは「一人で森にいる時間」と「焚き火を囲んだ人との会話」が繰り返される。最終日には、内省と言語化のサイクルから生まれた深い気づきにもとづき、現実に活かせる具体的な行動を決めてから帰るのだという。今回は二時間という、建長寺の森にてその一部を体験させていただいた。
お二人による簡単な説明があったのち、さっそく時雨したたる建長寺の境内へと足を運ぶ。

森に入る前に、まずはウォームアップとして二つのワークを行った。一つ目は、視野を広げるワーク。両腕を前方に伸ばした状態で、立てた人差し指に注目する。そこからゆっくりと水平に離していき、見えなくなったところで止める。次は同じことを上下の動きでもって行うというシンプルなワークだ。自分の周辺視野の領域を体感することで、視界の狭さに気づくだけでなく、より広い視野でもって自然と向き合えるという。

二つ目は、五感を「ひらく」ワーク。気に入った木の前で立ちどまり、ただ静かにその木を観察したり、目を閉じてただその空間に身を委ねたり。幹に生えたコケが成していた不思議な模様、風に運ばれてきた微かな線香の香り、じっとりと境内にそぼ降る雨音など、少しずつ自分の感覚が研ぎすまされていくのを感じた。

「普段一日の中でどれくらい頭を使って考えていますか?」
この菊野さんの問いに参加者の一人が「九割ほど」だと答えたとき、普段自分も朝起きてから夜寝るまで考えている時間が多すぎると気づく。視野も、パソコンやスマホばかり眺めるトンネルビジョンになりがちだ。しかし、森の中で暮らす生き物にとっては、思考や一点集中の視界は特別な場合に限られる。森に入らせていただくときは、私たち人間も感覚をひらき視野を広く持つという森のモードに倣うことで森との同調性を高めていくことができるのだ。
少しずつ「感じるモード」に切り替えたうえで、境内の外へと移動。建長寺の周りはハイキングコースとなっていて、手つかずの自然とは言わないが、草木が鬱蒼と生い茂る。
ひらいた五感でもって、森へ入る準備をした。

森との対話、大地の呼吸
ここからは各々の行動の時間となった。菊野さんからのインストラクションはいたってシンプルで、「森にお邪魔させていただいている」という謙虚な気持ちをもちつつ、ゆっくりと歩を進めながら、全身でその空間を感じとる。気に入った場所が見つかったら腰を下ろすなどして止まり、静かに「森との対話」を味わう、というものだ。
ここから下に、筆者の森リト体験の様子を少しばかり書こうと思う。言うまでもないが、森での一時間は「感じるモード」のまま過ごしたため、そこで受けとったことを言葉として表現するのは難しい。それをふまえたうえで、少しでもその体験を想像し、感じとってもらえたら嬉しい。
*** 体験 ***
まず、檜の大樹が立ち並ぶ一角で足がとまった。しとしとと降る冷雨の中、一本の檜に目がとまる。そっと添えた手のひらから柔らかな樹皮の感触が伝わってきて、力強くそびえる幹との対照性が面白い。しばらくその場に立ち、檜の存在感とその柔らかな木の香り、枝葉から滴る雫の様子に意識を傾けてみる。

その後さらに歩を進めると、竹林の脇を上がっていくとある石階段に目がとまった。なんとなく惹かれたのでそっちの方向へ。登っていく最中、段のすき間から生える草に目がいき、その小さな生命力を噛みしめる。登り切り、さらに道なき道を進んでいったところで、開けた空間が姿を現した。

そこは岩壁と木々に囲まれたテニスコートほどの広さの空間で、奥には苔むした墓石のようなものがいくつか離れて立っている。その森閑とした空間を覆い包むように一本のもみじの木が生えていた。とても不思議な空気をかもした木で、少し距離をおいて観察したのち、近づいてみる。下からの風景はまた違うことに気づき、木の幹にもたれかけてみた。
何分経っただろうか。しばらくすると、自分の背中ともみじの木の境界がわからなくなってきた。自分が木となり、木が自分となる。高いところの枝葉にしたたる雨を、まるで自分の身体のように頭と肩で感じはじめた。
そして、その木に流れる一種のエネルギーと濡れた落ち葉に覆われた大地との一体感のなかに、呼吸のようなものを感じた。その森、そして大地の呼吸でありながら、自分の呼吸でもあった。

******
ごちゃごちゃ、ありのまま、偉大なつながり
森との対話の後、いまだ体中の細胞がひらいたような感覚を抱いたまま屋内に戻ると、各々の体験を共有する時間が設けられた。森に生える木が一本一本ユニークであるように、似た体験をした人たちの間でも捉え方は様々だったようだ。
「ある小さな木が紅葉していた。それを見たときに『この木はさっき見た木と同じ?』などと考えてみたが、どっちでもいいことに気がついた。見たものを勝手に決めつけ、境界をつくっているのは自分なのだと」
こう話したのは参加者の男性。森で見かけた「もの」を一種の「カテゴリー」の箱に整理しようとした自身の思考プロセスに気がついたというのだ。
これを聞き、近代西洋思想の始祖の一人、ドイツ人哲学者イマヌエル・カントの認識論を思い出した。世界に「存在している」と思っているものは、実は私たちが五感でもって知覚した情報を頭が処理した結果にすぎない、というもの。言い換えれば、ほとんどの情報が脳内フィルターによって整理されてしまうため、事物“そのもの”をインプットすることは不可能に等しい、ということでもある。
この「情報の仕分け」作業だが、誰もが日常的に行っている習慣ではないだろうか。
通勤中に、路肩に生える街路樹を「街路樹」としてではなく「今、目の前に存在する理解しようのない事物」として捉え始めたらどうだろう。脳が疲れて一日を過ごすのもやっとかもしれない。私たちの五感は絶えず膨大な量の情報を知覚していて、それらをわかりやすく脳内の収納スペースに分別することで、必要な情報とそうでない情報を効率よく選別するクセがついているのだ。筆者が最初に訪れた場所でも、ウォームアップで行った二つ目のワークを踏んでいなければ、檜の木々はただの「横に並んで生える脇役」だったかもしれない。

この効率型思考は、生きていくうえで欠かせないものだ。なぜなら、情報化や多様化によって世界は絶えず複雑になっているのにも関わらず、社会は「雑」という概念や状態がまるで文明性の対極にある気味の悪い物の怪であるかのように否定し、暮らしの末端に至るまで徹底して整理整頓することで、野蛮的な「煩雑さ」を隅に押しやってきたから。単線的な合理主義の追求によって生まれた“反生き物的”現代社会に生きる私たちの多くは、決まった場所に物を整理し、決まった道を歩く町生活に慣れてしまったため、箱詰め思考に方がはるかに役に立つ。
しかし、このような世界との付き合い方は、同時に多くのものを見落とす原因ともなる。そのことを教えてくれるのが、森なのだろう。
多種多様な生きものが乱雑に共生し、複雑なシステムを形成している「森」。そのダイナミックな流動性のなかでは、物事を固定された箱に詰め分けようとする論理や思考はあまり意味をなさない。そこで必要になるのは、「ごちゃごちゃ」に対応するため、「ありのまま」を受けいれる、ということだろう。このフォーラムの他セッションでも“ネガティブ・ケイパビリティ”という能力がサブテーマとして挙がっていたが、まさにこのことであるように感じた。
感じるモードに切り替え、少しだけゆっくり歩いてみる。そして、普段無意識のうちにつくってしまう境界を認識し、感覚をひらくことで、自分と世界の“あいだ”の部分に意識を向け、対話する。そこにすでに存在していた大地との深いつながりに気がつく。
この体験セッションに参加し、二時間という短い時間ではあったが、とても貴重な気づきと向き合うことができた。

心の中に自分だけの森を育んでいく旅
では、なぜ今、森リトの需要が高まっているのか。
それは、現代人が抱える根源的な違和感と関係しているのかもしれない。来る日も来る日もパソコンと向き合い、人工物に囲まれた空間の中でひたすら頭を使って考える。中沢新一の言葉を借りると、人間が人間という小さな殻の中に閉じこもってしまうことで「精神のエコロジー」が少しずつ蝕まれていくというモヤモヤともいえる(Ecological MemesのHP参照)。これこそ「木を見て森を見ず」状態。そんな殻を内側からひらいてくれるのが森なのかもしれない。

森のリトリートでは、単純に自然とふれあうことで疲労やストレスを癒す、といった一時的な身体回復(だけ)ではなく、森と共に時間を過ごすことで得られる深い安心感や自分の内なる世界とのつながりと対話をしていくチャンスが与えられる。
感じることの神秘や悦びを教えてくれる森。
「ありのまま」の大切さを体現してくれる森。
大地と自分の呼吸が同調する森。
そして、入ってみて感じとった森のエッセンスを「自分だけの森」として心の中に育んでいく。森を出たあとも、自分はどうありたいか、社会における役割は何なのか、心の森の声に耳を澄ませてみる。
そんな旅のスタート地点に立つきっかけが、森のリトリートという体験であるように感じた。

森の民としての感覚を取り戻していく
今、世界中で注目を集めている自然でのデトックスやリトリートだが、日本という環境で自然と向き合っていくということに、どのような意味があるのか。
日本列島では縄文時代には森と共に暮らし始め、火を燃やすために必要な木をいただき、山菜やキノコなどを食料としながら適切な手入れをすることで、森・地域の自然・土着の文化間における持続可能な共存関係を保っていた。
資源だけではない。日本語の表現が元々「盛り」から来ているように、木々がこんもりと盛り上がり深々と生い茂る森は一歩足を踏み入れるとひんやりと薄暗く、どことなく不可解で神秘的ではないだろうか。事実、日本中の山岳信仰では森に精霊や神々が宿るとし、人間の力の及ばないその空間は畏怖・畏敬の念とともに神聖視され、人々の心の支えとなってきた。
しかし、時代の流れとともに「森」は人間の制御の対象となっていく。平安時代の建築ブームに相まって加速した乱伐、天然林を建築用材となるスギやヒノキと植え替えたにもかかわらず、安価な外国産木材の流入によって今や手入れもせず放置されている人工林。文明による森林破壊は人新世の悲しい象徴でもある。
本来のエコロジーが失われつつある今、人と自然の関係性が問われている。

そんな時代に生きる私たちだからこそ、裸の気持ちで森へ。森羅万象の静かな息吹を肌で受けとめれば、その全体性のなかに身をおく自分の呼吸もおのずと聞こえてくるはず。
ひとりひとりが心の中に豊かな森を育んでいけたら、なんて美しい世界になるだろうか。
TEXT BY SHUHEI TASHIRO
PHOTOS BY KEITA FURUSAWA
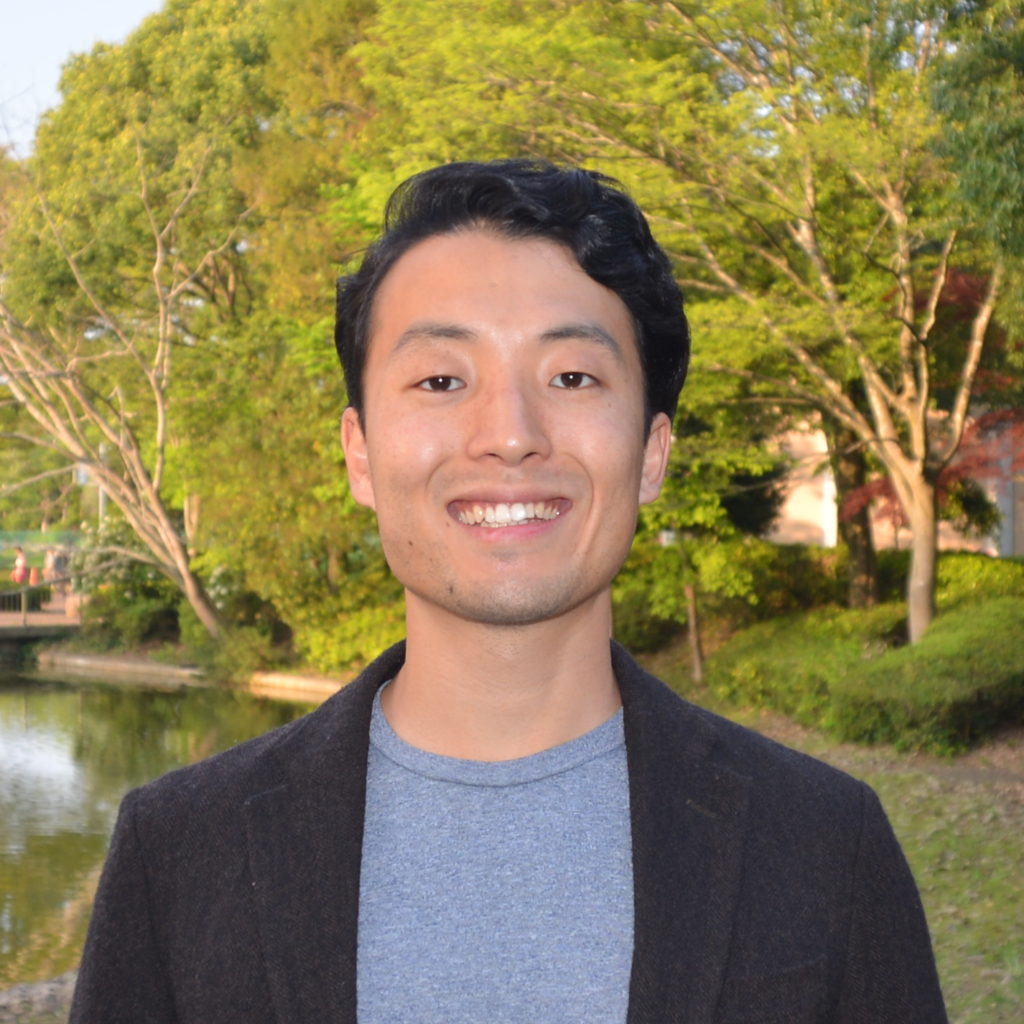
田代 周平 Shuhei Tashiro
一般社団法人 Ecological Memes 共同代表。
国際環境NGO Sustainable Ocean Alliance 日本チャプター共同発起人・代表。
ハイデルベルク大学大学院人類学修士課程在籍。
大学時代は、オランダ・ユトレヒト大学にてリベラルアーツを学びながら、同時に戦略コンサルティングファーム The Young Consultant に勤め、プロジェクトリーダーとして学生チームを主導。大学卒業後は、農業体験プラットフォーム WWOOF でのボランティアを通し、ポルトガルにおけるパーマカルチャーや自給自足生活の世界を肌で学ぶ。その後、船旅での地球一周を経て、領域横断型プロジェクト Ecological Memes に参画。現在は同団体の共同代表を務める。他にも、幼い頃からの海への愛から、日本における海洋課題に着目。国際環境NGO Sustainable Ocean Alliance の日本チャプター立ち上げに従事し、ボランタリーチームと共に若者と海洋をつなげるプログラムを開発・実施している。2020年秋より、ドイツ・ハイデルベルク大学の人類学修士課程に在籍。民俗学・エスノグラフィーの観点から、人間と自然の関係性を研究中。趣味は、音楽とダイビングと日曜大工。

