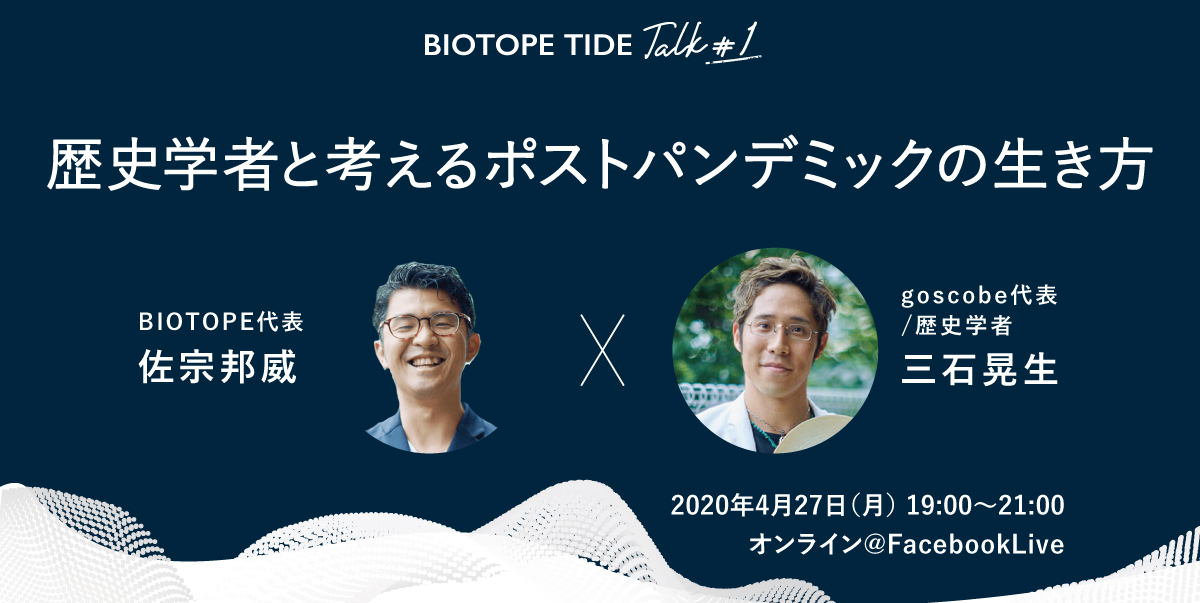2020年4月末に株式会社BIOTOPE代表の佐宗邦威氏と株式会社goscobe代表かつ歴史学者である三石晃生氏の対談がFacebook Liveで行われました。対談では歴史的な視点からパンデミックを扱い、私たちがコロナ禍をどう捉え、どのように生きていくべきかについて議論されました。本記事では、この対談「歴史学者と考えるポストパンデミックの生き方」についてレポートします。議論の全貌に興味が湧いた方は、ぜひポッドキャストへ!
スペイン風邪が起きた時の統治から考える社会変化のインパクト
まず、1918年のスペイン風邪を考察してみた。アメリカ兵士から戦争を通じて広がっていったが、スペインが情報を出したが故にスペイン風邪と名付けられた。ちょうど第一次世界大戦とセットになってしまったため、その影響は甚大だった。では、スペイン風邪は社会にどのような影響をもたらしたのだろうか?佐宗氏の問いかけから始まる。
三石氏はまず、疫病が起こると大きな政府にならざるを得ないと指摘する。なぜなら、政府は疫病を抑えるために力を持つようになるからだ。小さな政府では戦争も疫病も解決することができない。
さらに、戦争と疫病の共通点として、疫病や戦争によって問題が起こるのではなく、覆い隠されていた問題が露呈してしまうことが挙げられた。当時、アメリカのウィルソン大統領は、モラール法という法律(真実であっても国家に対して冒涜であることを出版したのであれば、20年刑に処される)を鑑み、第一次世界大戦の真っ只中に兵士の間で広がっていた熱病を表には出さなかった。このモラール法のように元々問題をはらんでいたが、それまで覆い隠されていた問題が露呈するのである。
佐宗氏も世の中には光と影の両面があるにもかかわらず、満ちているときは、あらゆるものが覆い隠されていると指摘する。企業で例えるなら、儲かっている時には問題が明らかにならないが、儲からなくなった時に、トレードオフが発生する状況になると格差のような問題に直面せざるを得ない。また、気候変動の問題もある。今回のコロナを受けて、北京の空が綺麗になったことも、薄々課題意識を持っていたことであるが、誰も取り組んでいなかった。問題が明るみになることで、社会の変革のスピードを上げていく、もしくは変革を閉ざしていた壁がいつの間にかなくなっていく流れがあるという。
社会の変化を引き起こす要因はそれだけではない。社会の変化が起きるときというのは、人口が大きく減るときだと三石氏は指摘する。労働人口、農業人口、都市人口が減ると、その変化に応じて社会構造も変わってくる。すると、既存のシステムでは対応できなくなり、新しいシステムを取り入れる。つまり、イノベーションをどうしても起こさなければならない状態になる。アメリカの第一次世界大戦時にスペイン風邪で亡くなった兵士の数は、後のベトナム戦争の戦死者数と比べても七千人程度しか違わないという。兵士であると同時に労働の担い手でもあったため、アメリカにとっては大打撃であった。多くの死者が出たことは、国内の世論への影響ももたらした。上述のウィルソン大統領のモラール法は失策であり、死亡者を増加させてしまったが、そのままでは終わらない。我々はここで反省して、世界の戦争、そして病気にみんなで立ち向かっていく体制を作るんだ、とベルサイユ条約のように新しい世界を見ようという方向に進んだという。理念が加速したのである。ただ、スペイン風邪と戦争が戦後の新たな秩序に向けて動き始めたきっかけになったというより、元からやっていたアピールが大きくなったという。
一方で、当時の日本でもスペイン風邪による死者がでたものの、どうにも世界の変化というものを日本は感じていなかった。欧米とは異なり、日本は第一次世界大戦と同時期にスペイン風邪を経験しておらず、当時できつつあった世界の新しい秩序にシフトしなかった。欧米諸国は第一次世界大戦とスペイン風邪を同時に受けて、我々は手を携えていかなければならないと、新しい秩序を作るんだと思っていた。ところが、日本はベルサイユ条約の時に、ドイツ領の南洋群島を要望したが、それ以外の今後の疫病への対応や国際的な秩序においては何も主張しなかった。この日本と欧米諸国のギャップを抱えたまま、1941年の日中戦争、支那事変に向かってしまった。
この話を受けて、佐宗氏は今まさに第一次世界大戦後に起きた秩序の変化についていけなかったことで起こった悲劇が歴史のパターンとして見えたと述べる。今、日本では死亡者の数が奇跡的に少ないが、未だに要因がわかっていない。そういった状況がある一方で、このコロナの反省を得た国は今後どう変化していくのか、そしてそうした国々に我々は国際秩序的にどう付き合っていくのか、大きな問いが存在するという。
さらに、三石氏はいかに疫病を抑えられるかということが、社会的な地位に反映されると指摘する。日本が一番最初に統治した台湾の総督初代である後藤新平は元々政治家ではなく、細菌学の権威だった。台湾の統治を正当化させるためには、そこで病気が起こらない状態を作ることが重要だった。今回のコロナでも、アメリカはうまくいっていない、台湾は見事にコロナを抑えている。日本はというと、コロナを抑えられてはいるが、要因がはっきりしていないために評価されていない。国際的なリーダーシップをどの国がとるべきか、という話になったときに疫病をいかに抑えられるかどうかが重要になる。疫病に勝つということは、戦勝国と同義の意味を持つという。
ここまでの話を振り返ると、全体の群れとして、あるものに立ち向かっていく時、ガバナンスを上手く治めた国はある種、国際的な地位があがり、パワーを持つようになる。一方で、失敗した国は、大きな社会変化を引き起こし、イノベーションを起こすきっかけを得る。これだけをみると、どちらが正解で、どちらが不正解かが自明ではないと佐宗氏が述べる。どちらにせよ、パワーやエネルギーを持つことになり、その後の変化の中で国はどうなっていくのか、という大局的な問いが見える。そこで、日本が今の流れのまま、上手くいった理由はわからない状態でやり過ごすと、またスペイン風邪と第一次世界大戦で新たな秩序を構成しようと動いた欧米諸国とギャップを抱えてしまうのではないだろうか。センシビリティを持って注視していかないと、気がついたら世界が変わっていた、ということもあり得る。
ペストの歴史から考えるポストコロナの世界
次にペストが起きた時代の歴史を考察した。ペストでは世界人口の22%、ヨーロッパのイングランドとイタリアでは人口の8割が亡くなった。三石氏はコロナの広がり方はスペイン風邪に似ているが、社会的な影響や変化においてはペストレベルであり、次に来るべき世界はポストペストだと述べる。では、14世紀のペストによって社会にどのような変化が起きたのだろうか?
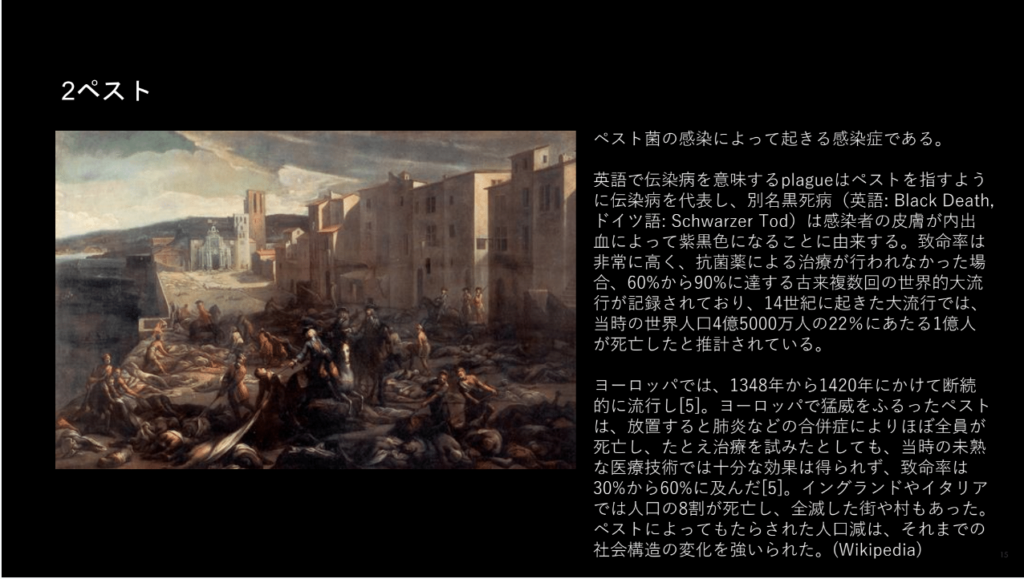
一つに、当時の封建社会がはらんでいた問題点が明らかになったことである。封建社会では、稼げば稼ぐほど農奴はどんどん豊かになるため、人口が増大していた。そうして人口が膨張して生産力がギリギリまで伸び、ちょっとした天候不順や不作でも大規模な飢饉に陥いる状態になっていた。これは現在の資本主義社会の問題とも似ている。誰もが資本主義に問題があると思っているが、次の選択肢が出せないまま飽和しているため、封建社会のようにちょっとしたことで均衡が崩れていく状態にある。このように封建制度の全盛期と資本主義の飽和状態は似ていると三石氏が指摘する。
二つ目に、宇宙としての教会が失墜したことを挙げる。当時のキリスト教的世界観でいうと、病は人間に神が下した罰であったが、聖職者もペストにかかってしまった。祈りと関係なく人が死に、それまで地方国家であり、共同体であった教会は何も解決してくれないことが明るみになった。すると、どうも違う共同体国家が頭をもたげ始めるという。自分たちが帰属する世界はキリスト教ではないかもしれないといううっすらとした気持ちを持つようになった。
三つ目に、ペストの拡大によって人材が減ることで、社会の枠組みが変わったという。人材が払底すると、既存の制度では雇用されることがなかった人を雇用するようになり、多様性を受け入れ、慣例を打ち破ってもいけるんじゃないか、という空気が出てくる。そこから社会の枠組みを変えていく原動力になっていく。封建的な身分制度、土地の制度が次の段階に進んでいき、英国であれば弱い王権になり、フランスでは農奴に依存した形の絶対王政になった。この時、国によってアクションは異なり、どこの土地にいても固有のイノベーティブな性質が見られたという。
佐宗氏はこの話を受けて、世界がこれから分極化し、異なるモデルを持ち、個性化していく動きが起こるのではないかと述べる。BIOTOPE TIDEではアメリカよりも中国やヨーロッパなどの様々な国を取り上げているが、国環境、文化、経済、政治に対する信頼感、地政学によってモデルがかなり変わりそうだという。3年くらい前から、アンチGAFAに始まり、個人の権利を大事にして、それをもう一段次のレベルに持っていこうとするヨーロッパ、AIを使いながら人民を全体として捉えていく中国、自由競争と資本主義を拡張していこうとするアメリカ、この3つの勢力が出てきている。日本のように特殊な立ち位置にある国は、今度どう進化していくのだろうとずっと思っていたという。
人口構成が変わるとパワーバランスも変わること、何かうまくいかなかったときに、それを支えていた権威が失墜すること、これらの二つのパターンが見えてきた。しかし、スペイン風邪では働き手が疾患していたが、コロナでは高齢者が弱いという特徴がある。もし働き手の人口に大きな変化がないとすれば、今回のコロナが社会にどのような影響をもたらすのか、佐宗氏が問いかける。三石氏は仮にコロナが収束せず、60歳以上の構成率が低くなると、日本の場合には支持政党の基盤の願いを叶えるために政治が行われているので、政治が大転換を起こす可能性があると述べる。
さらに、今回のコロナで特徴的だったのが、高齢層と若年層でお前らが拡散しているとお互いが思っている仲の悪さだという。コロナ禍では恐れの感情や普段何気なく思っていたことが明らかになると三石氏が指摘する。武漢の研究所からウイルスは流れていたとアメリカは言っている。ペストの時にも、ユダヤ人があまり死んでおらず、気に食わなかったからユダヤ人が毒を撒いているらしいという噂が流れた。満洲鉄道でペストが流行った時も、中国人たちは日本とロシアが自分たちで毒を巻いているのではないかと疑った。そこが驚異だからという理由で陰謀論となって出てくる。つまり、恐れの感情を顕にさせてしまうことだという。コロナでも去年くらいにはSDGsのような、世界は一つ!多様性!ということが声高に叫ばれていたが、実際にコロナがきたら内向きになり、国を閉じて分断が起きている。三石氏は自分たちの新しい秩序を作るということに本音で向き合わないと、次の世界にいけないと指摘する。
恐れに着目しなければならないということはとてもリアリティのある話で、その先に二つの道があるのではないかと佐宗氏が指摘する。まずは、人間性というものの再定義であり、例えばRedefine、Reflame、Recreation、Redesign、Regenerativeがあげられる。もう一つは人新世のように、もしかしたらウイルスと人間は共生する、多様性の文脈で捉えられるかもしれないという。人間側に向かう方向と、脱人間側に向かう二つが僕らの道の中にあるのではないか、考えさせられると佐宗氏がいう。三石氏は2分法的な世界観ではなく3分法的な世界観が必要だと述べる。自然か人間か、ではなく自然・人間・AI(機械)の3つからの再定義が必要だという。
疫病から内省を経てルネサンス「メメント・モリ」へ

木版画では法王とか王に手を繋いでいる者は全て、死者や死神であり、「みんなに死はやってくる、死を忘れるな」と教訓として描かれた。
続いて話題はルネサンスのメメント・モリへ。メメント・モリは死を忘れるな、という文脈の中にあった。木版画では法王とか王に手を繋いでいるのは全部、死者であり、死神であり、みんなに死はやってくるから死を忘れるなという教訓として描かれている。メメント・モリの対義語として、カルペ・ディエムという言葉があり、これは今を生きろという意味であり、死がすぐ隣にあることが「今を楽しめ」という意味につながってくる。メメント・モリをするからカルペ・ディエムがやってくるという。
現代の話でいうと、半年くらい前まで人生100年時代と言われていたが、疫病によって我々の中の観念が変化していることを表していると三石氏が指摘する。さらに、佐宗氏は人生100年時代、ずっと生きているということは当たり前で、ある種の生きる価値のインフレが起きていると感じていたという。しかし、今ではコロナによって、ずっと生きていることが当たり前ではなくなり、絶望を持ちながらも少し前向きにがんばってみようという空気を感じている。

左の絵はジョットが聖母子像を人間的に描いたとものだと言われている。右の絵はフィリピーノ・リッピが自身の妻をモチーフとして描いた聖母像だと言われている。
上記のマリア像の絵画は、プレペストとポストペストの違いを良く表しているという。左の絵はジョットが聖母子像を人間的に描いたもので、表情が堅いようにみえる。そして、イエスを膝に置いているだけで、抱いていない。ペストでは子供を捨てなければならず、親子の絆が断絶していた死の舞踏時代から、内省を経て描かれたのがタルクィニアの聖母像である。三石氏はルネサンスはペストなしでは存在できなかったと指摘する。ペスト時代では、自分たちってなんなんだっけということをメメント・モリで内省した結果、今を生きるということに気づき、理性の正解として人間賛美のルネサンスに向かっていった。自分たちは何なのか、自分たちが生きている社会は何なのかを再定義する社会において、それを淡く表現したのがルネサンス絵画であったり、人文主義だという考えだった。さらに、疫病の後に国がダメだとか、あれがダメだとかという話になるが、そうではなく、自分たちの表現技法や自分の声明としてのアートが出てくるという。
その話を受けて、佐宗氏はまさに今はそういった再定義の渦中であり、「起こっていることに目を見開いて見なければならない局面にある」と主張する。ただ、ステイホームをしていると、メディアを通して見る情報が多く、何一つリアルがない状況にある。生で見ることの衝撃によって時代の変化が起きやすいが、ステイホームがそれを遅らせていると感じる。三石氏もステイホームが可愛くキャッチーになってしまって、自分を深掘りにくいと問題を指摘する。ルネサンスは内に内に意識が向かう内省から生まれてきた概念だが、ステイホームは内省の時間ではないのだ。一方で、佐宗氏は他人や社会というものに影響を受けにくいタイミングであり、社会活動していたら考えられなかったことをゼロから考えてみるいい機会でもあるのではないだろうか。
以上、今回の対談をお届けしてきた。歴史のアナロジーから社会構造の変化、新しい秩序の誕生、顕になる恐れの感情、死生観の変化、人間性の再定義と話が多岐にわたり、重要な示唆がいくつも出てきたのではないでしょうか。みなさんが、現代はどういう時代なのか、どこに向かえばいいのか、良い未来をつくるために何が必要なのか、考えるヒントになれば幸いです。
Stay home, Stay thinking!
編集後記
最後に本記事の限界について少し述べたい。当然だが、本記事では文字数の関係で2時間に渡る対談の全ての内容を載せられていない。もし少しでも興味を持っていただけたら、ぜひポッドキャストで対談音声を直接聞いていただきたい。本記事が拾いこぼしたところにも重要な示唆が隠されているだろう。(舘尾ニコール執筆)